最初に復路(帰り道)から始めます。(反省の多い一日でしたので)
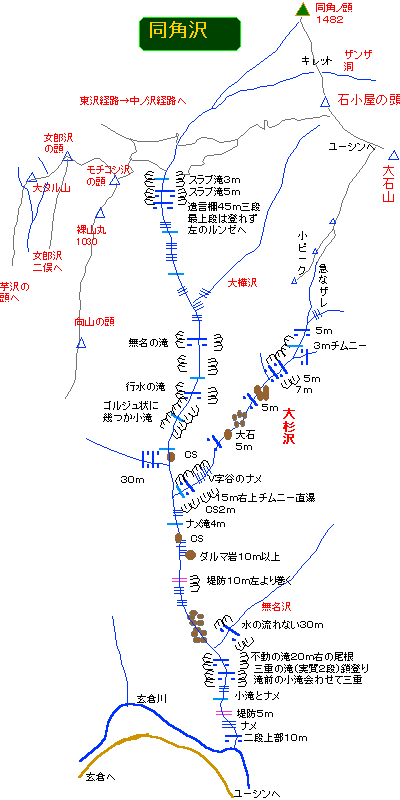 大杉沢はあっけなく終わった。
大杉沢はあっけなく終わった。時間を見れば午前11時少し回ったところだった。
玄倉からの帰りの時間はメモしておいた。
それによるとAM10時の次は15時06分(谷峨止まり)になっていた。
それまで四時間は有る。
早く帰りたいのなら一番は雨山峠を越えればよいのは分かっているが、晴れ渡った秋の空にもう少し浸るのも悪くないと思った。
丹沢の紅葉に足りないのは燃えるような「モミジの赤」だという。
しかし、この辺り(大石山付近)は丹沢では珍しく赤い紅葉が谷間を見渡せばソコココアソコというように多い。
地形図では表現されていないが、隣の大樺沢との分岐尾根には小さなピークが幾つも連なり、そのピークは樅の巨木と楓、モミジそしてブナの黄葉が合わさり、それがだんだら模様になって谷筋に広がっている。
ことに赤は日の光に照らされて蛍光色のように鮮やかに目に飛び込んでくる。
そばにある立木がじゃまになって、全体をちょうど良い構図にしたパノラマ写真に撮るのに適した場所が無いのがすこし残念ではある。
人間の目なら、そんな場合でもうまく脳内で画像処理をして
「おっ! こりゃあ綺麗」
と感じられるが、カメラに収めるとなるとそうは行かない。
沢を終わってから、小さな鞍部から大カバ沢上部のなだらかなカールから石小屋の頭に続く景色を眺め、同じような傾斜角のブナ林を暫く歩く。
もう少し先だと思っていたユーシンから同角山稜経由檜洞への登山道には突然ひょっこりと飛び出した。
「よし 芋沢の頭への尾根を下ろう」その時に決めた。
この選択は良かったか悪かったか!
丹沢をそれほど多くは歩いていないので早計だが、今までの経験の中では一番の悪路だったのは間違いなかった。
行かなきゃ良かったと後悔できるのが良かったと思う。
登山道に出た所からは目の下に石英閃緑岩が崩壊して砂になり、それが「あれっもう雪か」と錯誤させてしまうピークに紅葉と緑が混ざって見える。
大石山だ。
石小屋の頭も、そう遠くは無い。
反対方向に小さな上り下りを何回か繰り返すと「警告 小川谷への径路は・・・・」との松田警察署の標識が立つ東沢径路の入り口に達する。
同角の頭までは1.1kmの場所である。
ここから東沢径路に入る。
振り返る同角の頭、下降する向こうの青い空の下の石棚山稜
思わず辺りの風景に見とれてしまって小尾根を直進して進むと遺言棚直上に下ってしまう。
そこを下れば危ないから、途中から上流側に斜降するテープ標識を丹念に追う。
間違いさえしなければ同角沢までは何も危ないところはない。
東沢乗越への道は下りきったところから10m程僅かに上流の対岸にテープ標識がある。
そこに行く前に、遺言棚を見に行く。
棚の上は深い谷間が一望に出来る良い見晴らしなのだ。辺りの紅葉が楽しみなのだ。
だから見に行くと言っても下るのは面倒なので落ち口迄である。
遺言棚の上にはナメ滝が2個続いている。
上からは最初が3m、続いて6m程度、どちらも石英閃緑岩が水によって磨かれ、両岸は囲まれ逃れることが出来そうもないスラブの一枚岩で構成されている。
下に釜があるので、尻滑りの要領ですべり降りれば安全だ。
岩のフリクションは利きそうには思えるが、さて帰りにこの小棚が登れなかったらどうしようかとの懸念が滑り降りる最中の一瞬だけ頭をよぎる。
釜の淵は頬杖をつくのにちょうど良い。そこから身を乗り出して周囲を見下ろす。人の世界・社会生活でそれをやったら、ひんしゅく物だが、見下すというのはなんて気持ちが良いのだろう。それがここでは自由に出来るなんていうのがいいな。
高い棚の上から下方を見渡し、世界がパッと広がって自分が偉い人になったような気分を感じるっていうのは悪いものではない。
狭い谷間に滝の取り付きが小さく見える。
2段目上の深い釜が目の下に見える。
無理な芸当だとは思っているが、ここからその釜に飛び降り、一風呂浴びて周囲の紅葉を眺めるなんて芸当ができたら気分はなおさら良いだろう。
さて登り返しになる。
やっぱり懸念したとおり6m滝の登りは苦しかった。
摩擦をせいぜい利かせ、石英の粒に爪を立て、少し足をあげたら手のひらを返してマントリングしながら反対の足を引き上げ、フットスタンスを決める。
複数人だったら肩車で高度を稼ぐという手もあるが、もう5度傾斜がきつかったら、この小滝は単独では難しい。
磨かれたスラブには落ちてもぶつかりそうな石っころは何もないし、水はほとんど流れてはいない釜は水深が腰辺りまであるから何回滑り落ちたってせいぜい「手の皮を少しすりむくだけさ」と言うのが心強いけどネ。
もし何回か繰り返しても登り返せなかった場合には、左右には逃れられないから、そうなったら同角沢を登りに来る人を滝下の釜の中にじっと立ち、待つしかないだろう。
連休が始まる明日または明後日には人気の高い沢だから、少なくとも二組三組は入渓するに違いない。
それを確信してジッと待つのだ。
それまでの時間、ちょうど風呂によい大きさとはいえ、温泉ではないから何時までも浸かっているわけにはいかない。
辛くとも立ちんぼするしかやることはないだろうね。幸い風呂には縁が有るから寝ぼけたって大丈夫なように転落防止は万全だ。
東沢乗越迄の道はザレテいるが、道を失うようなことは無い。やや登り勾配程度の道。
誰かが吹き飛ばされた標識をかき集めてくれたのだろうか、警告板、小川谷方面、モチコシ沢方面等の標識が久しぶりに全部そろっている。
そこから通常は小川谷方面の東沢を下降するが、
今日は左折しモチコシの頭方向に進む。
道は細く険しいが取り立てて危険と言うところではない。
モチコシの頭で右折して女郎小屋の頭に向かう。
モチコヤ沢を登って裸丸山方面から東沢乗越に行こうとした場合、モチコシの頭から右折しなければ成らないが、直進する女郎小屋方向にも踏み跡が付いているので、思わずにして、こちらに入る人が多いことは十分に予測できる。
マシラもその手に引っかかってしまった事がある。それらの人の分も加えて、どちらかというと女郎小屋方面の方が踏み跡が濃い。
この分岐には以前は標識が立っていたようだが、今は標識の代わりにした立木が枯れて立っているだけだ。
いや、今日、5m離れた木陰に標識を見つけた。
字は少しかすれているが赤字で『東沢乗越』としっかりと書いてある。
枯れた標識杭の根本にそれを立てかけ、枯れ枝四本差し込み、少しくらいの風では吹き飛ばないように固定した。
そんな不安定な固定では何時まで持つモノか、捨て縄で更に固定すれば良かったかなと思ったのは、それからずいぶんと立ってからだった。
暫く歩き、何となくという雰囲気の女郎小屋の頭に立つ。
以前にこの地点から女郎小屋本流右岸の尾根に入り、踏み跡のある仕事道を二俣を経由して林道まで1.5時間ほどで下降したことがある。
今日はその尾根に誘い込まれず
(一回歩けば少しは勉強するのだ)
右に見えるピークを目指す。
あれが大タル山に違いない。
大タルってどういう意味なんだろう。
今日も地図は持っていないけど、頭の中に『右そして右』とたたき込んできた。
そうすれば立間橋方向に行くに違いないのである。
(これが大きな間違いの元だった)
それにしてもピークは直ぐそこに見えるのに、目の下の谷間が深い。
一体どうやって下って行くのが正解なんだろうか。
急に下降をはじめた踏み跡もこの辺りで不鮮明になる。
ザレた砂の上では体を止めようとしても足を取られ、立木にぶら下がることも再三発生して楽な道ではない。
しかし、要所要所に鉄杭が打ち込まれていて、今は残っていないが、そこにはかってはトラロープが張られていたに違いなかった。
その鉄杭が有るということは道が間違っていないことを示しているから心強い。
大丈夫だ。なんとかなるさ。
ザレた砂地を立木を確かめ確かめ慎重に下る。
そして両側に急なルンゼが食い込み、辺りの全てがザレ石砂で構成されるナイフリッジの乗り越しとなる。
対岸に2m程下がえぐられてオーバーハングしている木の根っ子が剥き出しになっている。
根っ子に捨て縄が五、六本架けられ揺れている。
おそらく、ここが女郎小屋乗越と言う場所だろう。
前を向いたままでは降りられず、乗越の中央部に降りなかったら間違いなく左右のどちらかを滑って落ちていくような恐怖の中、
三点確保、最後は四点確保(四つ足)のまま2mをずるずるを滑り、最後は飛び降りて乗越に着地する。
なんかあっても反転移動・瞬間移動も少しだけなら出来るとは思っていたが、本来確保用のロープを付ける場所だ。
だからこそ、木の根っ子に捨て縄を掛けて、登る場合の確保、下降の場合のそれぞれの支点にしているのだろう。
ともかくも嫌な下りだった。
こんな場所の下降はもう二度とごめんだな。
鞍部からの登り返しも最初はきつかったのが、それも段々緩やかになりヤレヤレとその時は思った。
これでおしまいさ。
木々の間から石棚山稜がかいま見える他は何の変哲もない大タル山山頂に立つ。
ここも踏み跡は鮮明だ。
この調子ならもう1時間も有れば玄倉川が女郎小屋沢に合わさる場所か、立間橋にある旧小川谷山荘地点のどちらかに着くに違いない。
どっちにするかは芋沢の頭で決めればいい。
もう楽勝さ。そう思った。
なだらかに下降して直ぐに左側に女郎小屋を登った際に上り詰めた急なルンゼと出会う。
ここも少し急な場所になっていて、右側の谷はその時に下降した沢だ。
深い砂ザレの谷間だが、砂を足で押し出すように下降すればよいし、下部には滝が数個有るけど、何れも踏み跡が鮮明に付いているので、それを辿れば容易に小川谷の終了点まで150m程の地点に降りることが出来る良い下降路である。
ここはパス
緩やかにちょっとだけ登り返したピークは3個の大きな石が転がり、辺りにはブナがはえる気持ちの落ち着くピークとなっている
緩やかに下って行くと再び前方が深く切れ込んだ。
「道は間違っていないよな」
周囲を眺め回し、対岸に見えるピークが進む方向に間違いないと確信したが、
下に大きな谷が横切っているのではないかと思わせるほど深く嫌な感じだった。
それでも、さっきの乗越もなんとか下れたし、今回だって、なんとかなるだろうさ。
心持ちか踏み跡が薄くなったような気がするけどいいや。
対岸のピークを眺め、下降ポイント見定め、その軸線をはずさないように急激な下降を行う。
途中までは立木が豊富にあり、まったっく問題なし。
問題になったのは下に乗越が見えるようになってからだ。
立木が少なくなり、枯れ木が目立ち、うっかり掴めない。
代わりになる藪竹も根が浅い。おまけに、枯れている物が目立つ。
岩がザレ、足を取られ、掴んだ竹が五六本全部パキパキ折れて手の中に枯れ木だけが残った時にはさすがにぞっとした。
幸い両の手で掴んだ片一方は残っていて余裕を持って止まった。
そこから見通す対岸は急な岩場になっている。
乗越の軸上中央には細い凹状があり、6m上がると木の根っ子に手が届きそうだが、そこまで登り返せるんだろうか。
それが不安だ。
登り口に枯れ木が2本立てかけてあり、あれはバランスを支える為の木梯子かも知れない。
そして、そんな先の事を心配するより、今が切実になってきた。
もう5m程で鞍部に降りられる。
しかし、掴む立木も竹も無くなった。
岩は握れば手の中でぼろぼろと砕けて砂になってしまう。
足下のスタンスは加重するだけでグッグと音を立てて崩壊していく。
これにナイフのような乗越が目の下に重なり、高度感も最高に高く
コワイ!。
このままじゃダメダ。下れない。
一歩上がって木の根っ子に掴まり、いったん体勢を作り直す。
辺りを見渡し、なんとか滑ることなくあのナイフリッジの上まで降りる手は無い物か。
一歩上がって左に3mトラバースし、ここから斜め下の乗越に走り込むって言うのはどうだろう?。
サスケの熟練者なら大丈夫さ。
でもヤッパし駄目だ。「サスケ」は失敗しても笑われるだけ済むが、ここではそれに「パンパカ」が加わる。
足場が決まらないから乗り越しに付く前に下に転落してしまいそう。
再びさっきのポイントに戻って、今度は右に移る。
軸線からは外れるが1m下に移れた。
そこで立木を放す。もう一歩下がる。
ホールドは砕けて無くなってしまった。
もう登り返すのはかなり面倒だ。足が滑る気がするし、スタンスも何時までも持たないに違いない。
いつまでもこの体勢を保ってはいられないぞ。
左に2歩三歩下降気味にトラバースし、最後は足が滑りはじめたが、勢いのままママヨと滑り落ちる。
ナイフリッジより1mはずれたけど這いつくばった姿勢で止まった。
ここは本来20m上の立木から確保してから下降するルートのような気がするな。
さて、次に登り返しだ。さっき見えた木梯子は単なる枯れ木だった。
辺りには人が登った形跡はなかった。
だけど何人もがここでやなんだ事は間違いない。左右の谷は深いが、下降は可能だろう。
どっか適当な所まで下降してから登り返そうかと思ったが、一体何処まで下降すれば良いんだろうか皆目見当が付かない。
そうすると一目目に登るのはダメだと決めていた直接登り返すルートにヤッパし目が行く。
触って確認すると急だが、幸いさっき下ってきたところほど岩が脆くはなかった。
擦ると何粒か脱落するような脆弱さは有るが、岩全体が崩れることはないし、岩場に体重もかけられそうだった。
ホールドは外傾しているが、石英閃緑岩のざらついた表面が十分なフリクションをくれそうだ。
人が登って出来た苔の剥げた跡が有るようにも見える。
たくさんの人が通っているのなら梯子、悪くても何本かのハーケンが有ってもおかしくない場所だが、手を着けたら一気に上の立木まで登り込む。
そこからは急な岩の間の藪を踏み分けて頂稜まで行く。
嫌な場所パートⅡ(嫌らしさではNoⅠ)がこうして、ようやく終わる。
カメラの残り枚数が少なくなったこともあるが、この間はシャッターを切る余裕も無かった。あ〜 シンド
 タルって、峠を指すって事を聞いたことがある。
タルって、峠を指すって事を聞いたことがある。女郎の乗越とこの乗越で囲まれたやっかいな山と言う意味で付けられたかどうかは知らないが、もしそうだとしたら大納得できる山名である。
そして、この区間は自らが蒔いた種ではあるが、丹沢で経験した中では今までで一番いやらしい尾根歩きの場所だった。
10mも行くと左から踏み跡が合わさる。
その踏み跡を逆に辿ると、その道は先ほどの乗越をエスケープして小川谷側を巻いて通る道になっていた。
道理で下降開始から道が薄くなっていたわけだ。
この道は楽ではないけど、きっと安全な道だと思う。
緩やかに登っていくと、その先のピークは気持ちの良い砂地になっていた。
先ほどの登りの余韻をここで冷ます。
思わず這いつくばって仰向けにひっくり返って空を見上げる。
朝方、小田原方面は曇りだったのが、立間橋を過ぎたことから晴れ間が出て、大杉沢では良い天気だった。
その天気が再び雲に覆われるようになったが、それでも秋の気持ちの良い高く青い空がまだ大半を占めていた。
さて本来、ここからはやや左手方向にP936mに向かうのだが、そんなことはちっとも気が付かなかった。
それに気が付く前に右手方向すぐの地点にピークが目に入った。
無論、持ちもしない地図でここから先の進路を確かめる事は出来ないし、
『今日は右そして右』と思いこんでいるから何も疑わずにそのピークを目指す。
この地点で既に道は間違ったのだ。
小ピークが行く手にあるように見えるが、方向が大きく違う。先に快適な下降路があろうはずがない。
直ぐに道が不鮮明になった。
煤竹が深くなり、左手を見ると小尾根が見える。 「間違った」
登り返し、ピークで踏み跡を見つけ、そこを下る。
誰かが歩いて付けた道には違いないが、それも再び煤竹の中に消える。
本来の道はもっともっと左なのだ。
この時点でおそらく3時のバスに乗るのは無理かなとは思う。
でも、明るい内に下ればいいさ。
日没まで、まだ4時間もあるし、焦ることは何もない。
幸い今日はユミコチャンに「帰りは六時頃になる」と伝えて有る。
それまでに電話のあるところまで (一番近いのは玄倉バス停) 下れば何の問題もないさ。
僅かにあった踏み跡も消えて、それからは煤竹の薄いところをより分けて下降する。
出来るだけ稜線を歩こうと思っても、その稜線ももう分からない。
こんな場合は、たいがい山の斜面を沢めがけて一目さんに下降している途中なのだ。
案の定やがて沢音が聞こえてきて
「ヤレヤレあそこは玄倉川か」
「それにしては川幅が狭いから県民の森下の小川谷か?」と言う感じ。
本来川と一体になっているはずの林道も見えないのが少し不安ではあるが、なにはともかく、沢にたどり着けば林道は遠くない。
まさか、そこが□□谷とは思いもしなかった。
だけど下り着いてみれば、そこは間違いなく「小川谷」だった。直ぐに分かった。
それも、先ほど通り過ぎた人がいたのか、岩の上に濡れた渓流シューズの跡が残る、小川谷の核心部だった。
あれだけ稜線を歩き、出来るなら立間橋付近で下降できたらと考えていたのに、以前に女郎小屋を登ってから対岸を下って僅か20分で下降した小川谷を、今日は何と3時間もかけて、いくらも変わらない地点に下降したのだった。
少し喜び 少しがっくり
でも、今日は時間があったら芋沢の頭経由で下降するか、小川谷を下降するか、どっちにしようかと考えていたので、ここでは両方が楽しめたという事で納得しようとおもう。
「えっ、どっちも中途半端だって」
そうだね。
でもいいさ。
下降した地点は間違っていなければ
「おお岩」の下付近になる。
思ったより出会いには近いはずさ。
小川谷なら今までに何回か歩いたことがあり、下降も遡行も余裕を持って行える自信は有るけど、朝から歩きづめで疲れているから無用な下りは怪我の元になる。
だからワナバ沢奥の5m滝は思いっきり巻いて分界尾根まで登ってから、その沢の右岸の上部は急な平板ザレ、そしてふかふかなに詰まった枯れ葉の道を下る。
通常の10倍ぐらい時間を掛かけたに違いない。
それでも、逃げられる危ないところは逃げるに限る。
こんな場合は焦るが負け。万が一って事もあるから、そうなってからでは時間がいくらあったって足りはしない。
そこからは下流には転がり落ちるような危ない場所は無く、下の釜目指して滑り台下りの釜ドッポン下りにする。
すこしパンツが濡れてしまうけど、それくらいなんぼでも我慢するさ。
ばんばんと水に入り、中ノ沢の出会い滝まで来てほっとする。
残すは穴の平沢の堰堤登って林道へ出るだけ。
たった200m程だが疲れるんだよな。安心してしまった体にはこれが。
今日はよく歩いた。朝6時40分からPM3時迄か。
最近の歩行時間4時間ぐらいの歩きに慣れた体には少しきつかった。
次のバスは4時6分、ここからなら1時間有れば余裕だ。時間はたっぷりある。
車も人も誰も通らない林道を「良い日・旅立ち」を歌いながら玄倉へ歩く。
音痴も気にならない。
小川谷の瀬の音に負けないぐらい大きな声で歌う。
山口百恵でも鬼束バージョンでも無い、ただの音痴バージョンだけどね。
それから、小さな願いがかなった日のうれしい気持ち 歌いたくなる様ないち〜にち〜 チェルシーの歌も付け加えて歌う。
歌い出しは忘れてしまったけど、そこはハミングでごまかす。
玄倉では三保にある学校からの帰りの児童が5人降りて家の方向に「チヨコレート」「グリコ」ってじゃんけんを繰り返して帰っていった。
この時間帯のバスはスクールバスの機能を果たしているのだ。
3時6分の谷峨止まりも、折り返して高校生の帰宅用になるんだろうな。
玄倉で日が落ち、石棚山稜が西の谷間上空にシルエットになってしまった。
早く帰らなくては 道草を喰って、かあさんにどやされるのは
子供もマシラも同じさ!
以下、往路について書き出します。
朝方、快晴だと言っていた天気は雲に押さえられて暗い。
その雲が立間橋を過ぎて川の上空が開けたところから変わってきた。
同角の頭辺りに日が当たり、徐々に山裾方向に向かって下降し始めた。
でも一方通行に回復する雰囲気ではなく、晴れ間の次には雲、雲の次には晴れと行った具合にだ。
この辺りの狭い上空では御殿場&小田原連合と県央の天気が何時もつばぜり合いを繰り返している。
青ザレ隧道から逆U字峡谷に入る。
ぼちぼち紅葉がこの辺りに降りてきても良い季節になったから、その見物をしようと思った。
予想通り、赤や黄色に木々は色つき始め、もう1週間もすれば、この辺りの紅葉は最高潮に達するだろう。
ただ、温度差が緩慢に変動する丹沢では全部の草木が同時に色づくなんて事は滅多な機会でもない限り無い、というのが玉に瑕と言うところだ。
水量が減った河原は足を濡らすことも無く、モチコシ沢出会いを過ぎ、向山滝下も楽々通過、全部で3カ所有るへつりも今日は一カ所だけで、ここさえも濡れるのが嫌なら水に足を突っ込む必要がない。
白い砂と大きな岩の谷間と流れの止まったかのような深い瀞、切り立った両岸の木々の色つき、さすがに丹沢でも、この場所のような眺めを得られる場所はそうは無い。
これが林道から僅か数百mの位置にあり、晴れた日に限るけど、玄倉第2ダムが放水さえしていなければ、見たい人に、その気のある人だけに景色を公開しているのだ。
(モチコシ沢より奥、玄倉ダム迄は危ないから、馴れない人はモチコシ沢出会いから引き返すべきと言っておきます)
玄倉ダム下のアッチガ沢の地点でいったん林道に上がる。
それから隧道を3個くぐって振り返る。
もう少し歩けば同角沢の出会い地点に達する地点である。
この振り返った地点のちょうど今の季節の風景が【山北町観光協会】の【やまきたのハイキング】というパンフレットの一面の全部を飾っている。
さすがに専門家が撮影した画像は赤、黄色、水の青、川砂の白とコントラストが素晴らしく、こんな写真を撮りたいと思っても素人が5分10分で取るなんて絶対に無理だと思う。
シーズン真っ盛りの天気の良い日に、朝から身構えて光のコントラストが最高潮に達した瞬間を取るなんて素人の出来るまねではない。
そのパンフレットをよく見ると川が左に曲がって下る中央の上の赤い楓の葉の奥になにやら滝様なものが垣間見える。
そこには一体何が有るんだろう。
以前にも気になっていた、その地点を探るのも今日の予定の一つだった。
隧道入り口に戻り、川に向かって下降する。
ここから下る人も多いらしく、ちょっとくたびれているがクレモナロープがスラブ岩の上に残置されている。
ただ、全体重を架けるにはあまりにも心細く、触るだけにする。
川に降り、石の間を100mも進むと予想通り対岸に滝が現れる。
出会いは10m程のヌメった滝で、ここは右の草付きから入り、中段から流れの中を水を浴びないようにして登り切る。
そこから草付きを左に5m移動する。
傾斜は緩いが草付きの泥は、ようやく岩にへばりついているだけで、体重をかけるとこそぎ落ちてしまうから慎重な足裁きが必要だ。そうして達した地点は滝の広場になっている。
まず左が本流に相当する。
急な赤っぽい岩のスラブになっていて高度は45〜50mというところだろう。
角度おおよそ80度以上、岩は逆層気味で、これを登るには相当な努力を要すると思う。
見上げた滝の上は一面のブルースカイの秋空で覆い尽くされる。
滝から上の沢は浅く、それほど行かない内に流れは消えてしまいそうな雰囲気だが、ここからは想像でしかない。
別に右20m程中段から水が滴り落ちている。
水量は左より多いくらいだが、上には沢の形態はなく、湧き水がここから一気に落下しているだけの物だろうと思う。
その流れの10m右にもう一本細く水が流れる。
ここも20m以上の落差はありそうだ。
これらの滝が全てこの滝広場に集積してから下の滝を通って玄倉川に流れ落ちている。
この背景が有るから、それが直接に表に出てくることは無いが先の観光パンフレット写真に深みを出しているんだろうと思う。
そこに滝があるかどうかを撮影した写真家が感じたかどうかは知らないが、たかが観光写真といえどもヤッパし、プロの力はそれらの効果を鋭く感じていて深いと脱帽する。
下ってきた道を元に辿って林道に戻る。同角沢までは百m程、直ぐだ。
 大杉沢は同角沢の支流に相当し、石小屋沢の頭辺りに突き上げている。
大杉沢は同角沢の支流に相当し、石小屋沢の頭辺りに突き上げている。ものの本によると急峻でおもしろい沢だという。
アプローチは当然、同角沢に入る事になる。
見かけ倒しぐらいに見た目より易しいF1を越え、スラブ樋を左に巻いて堰堤を一つ越える。
続く三重の滝は鎖を頼りに登る。昭和30年代に付けられたという鎖は未だに健在で、これがなかったら面倒な登りになる。
ところで、丹沢の幕開けの時代はとうに通り過ぎてしまったから、かっての沢のブームの時代に取り付けたこのような鎖を今の時代に付け換えようと考える人はいないだろうな。
そして、この鎖は一体何時まで持つんだろうか。
続いて不動の滝の20m、次々と滝が現れるから同角はおもしろい。
前回はここで残置のカラビナを2枚回収したけど、今日は何もなし。
だから、滝に触れもせずに右を巻いて上に出る。更にナメが続く。ナメの中にはのっそりとイワナが泳ぐ。
前回と同じように囲い込んでつかみ取り。
同じイワナかもしれない。
そして今日も触るだけで2匹を逃がす。
しつこく追っかけている時間もない。
次に唐突に堰堤が現れる。
この辺りに玄倉第2発電所の送水管敷設工事跡が有るそうだが。おそらくこれが敷設管の外装だ。
続くだるま石辺りの大岩のゴーロナメは石と隠れっこするように岩の間を縫って進む。
少し進んで下に小滝、上にも小ナメ滝の有る地点で右手から今日の目的に大杉沢が入り込んでくる。
ようやく大杉沢だ。
出会いでは水はほとんど無く、のぞき込んでも
『これが大杉沢か!』ときずく程度の小沢である。
大杉沢
だけど、一歩入ってみれば分かる。
出会いの滝の難しいことが。
その滝に近づく為に手前のCS滝(2m)を乗り越える。
CS滝って好きじゃないけど、ちょうど良い手がかりがあって懸垂の要領で乗り越える。
F1は高度差15m
滝の部分だけなら13m程度かも知れない。
落ち口から続く両翼は更に10m程傾斜を落とさずに上に向かう。
滝は左からかぶってくる岩と垂直な右の岩の間のチムニー状の部分を登ることになる。
右の岩には、もう一本右上がりの溝状が刻まれているが、完全に外向きだからそこを登るのは難しい。
チムニー部は易しいかって言うと、そうはいかない。
チムニーに落ち込んだ水は15mの間ずっと登はん者の頭を打ち続けるに違いないし、チムニー状と言ったって体が入ってオポジション登りが出来るほどには広くない。
たとえ突っ張りの姿勢が出来たとしても、水に打たれたヌルヌルの壁はそれほどの摩擦力をくれるはずもないし、
途中にはCSが挟まっていて自ずとそこで姿勢を立て直す必要が生じする。
こんな逃げ場の無いチムニー登りをずっとしなければ成らないのだからこれは辛い。
この滝って登る奴は、いないかって?
それが違うんだよな
丹沢界隈きって難しいなんて称されると
「それなら俺が登ってやらあ〜!」っていう人が押し寄せるって図式で、この滝はかなり登られているとおもう。
落ち口のハーケンに結わえられた何本ものシュリンゲの束がその証拠を示す。
ただし、それだからと言って大杉沢がたくさん登られているかと言えば、それはまた別の話しになり、シュリンゲの束は出会いの、この滝だけが、同角沢を登るついでに登られている事を表しているとも言える。
とうぜん、このような滝は、見るだけだ。
CS滝は懸垂しても届かない足をぶらぶらさせて飛び降りる。
出会い左の小尾根から落ち口までの高さを登った後で踏み跡を辿って、15m滝上のナメ滝の上におりる。
踏み跡と言っても例の滝の上辺りは外傾している。
掴む物は何もないので高度感に負けたらこの場所はトラバース出来ないに違いない。
正直言うと、もう少しで負けそうだった。
ナメスラブを滑って落ち口まで戻り、岩が裂けたかのようなチムニーの最上部のシュリンゲの束を手にホールドして下をのぞき込む。
4m程下にがっちりしたCSが挟み込まれていて、そこに落ち口から落ちた水がダイレクトにぶち当たり、外側に分けられた水は、そのまま何処にも触らずに下に落ちていって、滝全体がオーバハングしていることを示している。
シュリンゲは新旧様々なものが6本は掛かっている。

 左に涸沢が上がる場所にある平板7m滝は傾斜がきつく登れそうもない。
左に涸沢が上がる場所にある平板7m滝は傾斜がきつく登れそうもない。



